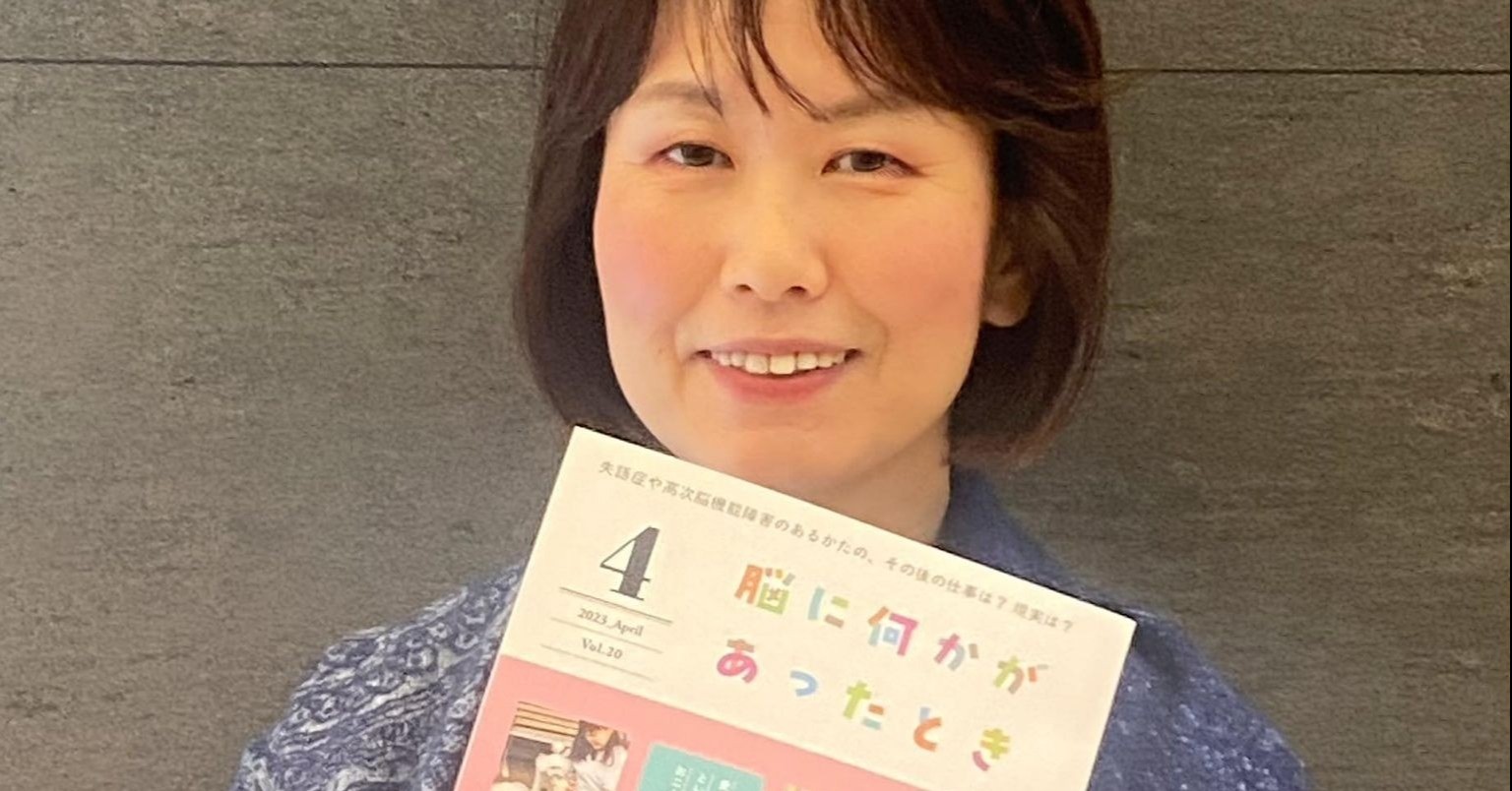4月25日は「失語症の日」。失語症者らを支援するNPO法人「Reジョブ大阪」代表の西村紀子さんは、脳に疾患を抱える患者の声をまとめた冊子「脳に何かがあったとき」をリニューアルした。編集メンバーに雑誌「anan(アンアン)」元編集長、能勢邦子さんが参画するという豪華な布陣。2023年4月25日から、全国の医療機関などで600冊を配布する。
「読みにくい」冊子を魅力的に

「患者のリアルな声を伝える冊子のリニューアルをお願いできませんか」。西村さんは2022年12月、オンラインで能勢さんに依頼した。断られるに違いない。そう思いながら。しかし、返ってきたのは「やりましょう」という快諾だった。
西村さんは、言語聴覚士。Reジョブ大阪代表として、突然障がいを抱えた患者や家族のサポートを中心に活動している。患者のリアルな声を届けることで、失語症などに対する社会の理解を深めようと、2021年から冊子を発行。既に19号を数える。
「西村さん、この冊子、周りに薦めたいけど読みにくい」。ある日、インタビュー取材した患者からこんな声が届いた。ショックが西村さんを襲う。

せっかく取材しても、冊子を手に取ってもらえないなら意味がない。西村さんはリニューアルを決意して、能勢さんを突撃したのだった。西村さんの冊子は部数100冊で、「anan」は16万部超え。
この落差を埋めたのは、能勢さんの父親が失語症を患っていたという共通項だった。能勢さんは2021年、父親の回復に効果があった方法をもとに「失語症からの言葉ノート」(コトコ)を出版していた。
西村さんと能勢さんに重なるもの
冊子リニューアルは急ピッチで始まった。「今までの冊子を送ってください」と能勢さん。そして、「内容は良い。編集とデザインを変えたら、もっと伝わる可能性が高い」とコメントした。

「最初はお金もいるし、覚悟もいるけれど、私には『ここまでいける世界』がわかります」
そんな能勢さんの言葉を聞いて、西村さんは「リハビリと同じだ」と直感した。患者の様子を見れば、どれくらい努力すれば、どのように回復するか、西村さんはイメージできる。
それを患者が信じて、やってみるか。信じられず、リハビリしないか。「回復は信じることから始まる」ことを、西村さんは知っていた。
「私には見えていない能勢さんの編集の世界を信じるかどうか。信じようと決断しました」
予算を提示すると能勢さんは、できることとできないことを回答しながら、サポートを約束した。リニューアル第1号の特集は失語症。「聞く、話す、読む、書く、計算する」のすべてが難しくなった状態をいう。意思はあるのに、伝えられないところが患者にとって最も辛い。
西村さんは「障がいや病気ではなく、その人を伝えたい」という編集方針で挑んだ。
ライター2人は、西村さんが人脈をたどって見つけた。その一人、まるやまみなみさんは普段、ドラマの脚本を書く仕事をしている。イマジネーションの世界で物語を紡ぐが、今回は現実の話を丁寧に聞く仕事。

「とにかく能勢さんに食らいついていこうと思いました。取材対象者がすごいことを乗り越えているので、取材しながら、私ももっと頑張ろうと思えるんです」と、まるやまさん。
能勢さんは「私が関われるのは、リニューアル第1号だけ。すべてをあなたに教えます」と、まるやまさんに宣言し、メール返信などを最優先に対応してくれた。
大変な作業も「そよ風」のように
能勢さんとの作業は、学びの連続。例えば、インタビューはオンラインではなく、実際に足を運んで対面で聞く方が「断然良い」と教わった。西村さんも実際に取材を経験し、対面インタビューの方が「理解が深まる」と感じたそうだ。
また、西村さんは締め切りに追われていた時、ひとつの言葉に出合った。「西村さんにとって『津波や嵐』のような出来事でも、能勢さんにとっては『高原のそよ風』やで」
この言葉をきっかけに、西村さんの心境が変わったという。それまでの「大変だ」に代わって、「こんなこと、そよ風だよね」と口にするように。冊子に登場する失語症者らの大変さを思うと、「そよ風」だと思えた。それに、心の中には頼れる能勢さんがいた。
完成した冊子は、A4サイズ、26ページ。29日間のクラウドファンディングで、制作費など目標の80万円以上を集めた。

2020年に認定された「失語症の日」は、西村さんが呼びかけ人のひとり。「知人に『失語症を真面目に伝えようとしても、なかなか理解してくれないよ』とアドバイスされ、遊び心を込めて『425(し・つ・ご)』です」
「突然の事故や病気で、いつ誰が脳に疾患を抱えてもおかしくありません。そんな時、病気について事前に知っている人と知らない人では、『その後』が大きく異なるんです。何も知らない場合は絶望してしまいます」
冊子を読むことは、将来に向けた心のセーフティネットとも言える。取材した人生ストーリーから「生きるヒント」を読み取ってほしい。西村さんはそう願っている。