話す時に最初の1音を引き延ばす(伸発)、最初の音を繰り返す(連発)、言葉が出てこない(難発)といった症状が現われる吃音症。当事者の中には言葉がスムーズに出ないことから、心ない視線を受け、話すことに恐怖を抱いている人もいる。
今回取材したハルキさんも、吃音症に悩まされたひとりだ。しかし、大学生の時に抱いた「教師になる」という夢を叶え、吃音があったからこそ得た学びや出会いへの感謝を言葉にする。
生き様に惚れた恩師との出会いで「教師」が将来の夢に
物心ついた頃から、吃音症であったというハルキさん。例えば、「おはようございます」と言いたい時には、「お、お、お、おはようございます」という連発や「おーーーーはようございます」といった伸発、声が出せなくなる難発といった症状が出ていた。
もともと人前に出ることが嫌いではなかったが、学校生活では吃音症であることから、やりたい気持ちを封じ込め、生徒会長や応援団長への立候補を断念。
理解ある仲間に囲まれていたものの、自己紹介や授業での音読、発表、卒業式での呼びかけなど、大勢を前にして声を発する時には強いプレッシャーを感じていた。

そんなハルキさんが、教師という夢を抱いたのは大学3年生の頃。当時、ハルキさんは就職活動を前に、「学生時代の部活とは違い、社会人は努力が直接報われない世界なのでは…」という不安を抱いていた。
しかし、努力を結果に結びつけたような教員生活を送る教授との出会いを経て、考え方が変わった。生き様に惚れ、自分も教師になりたいと思った。

「それに、使命感のようなものも抱きました。自身が吃音症であるからこそ教師になって、みんなにもっと吃音について知ってもらおうと思うようになったんです」
大きなプレッシャーを感じて涙した、卒業式での呼名
しかし、教師は「話す仕事」。実際になってみると、葛藤の連続だった。中でも、教科書の範読(見本の音読)や保護者との電話連絡、6年生担任時の卒業式での呼名などは、ハルキさんにとって大きなプレッシャーに。
「特に卒業証書授与の呼名は、人生の中でもかなり大きな試練でした。厳粛なムードである卒業式で、多くの保護者、教員、卒業生、在校生、来賓がいる中、たった1人で声を発しなければならないので…」
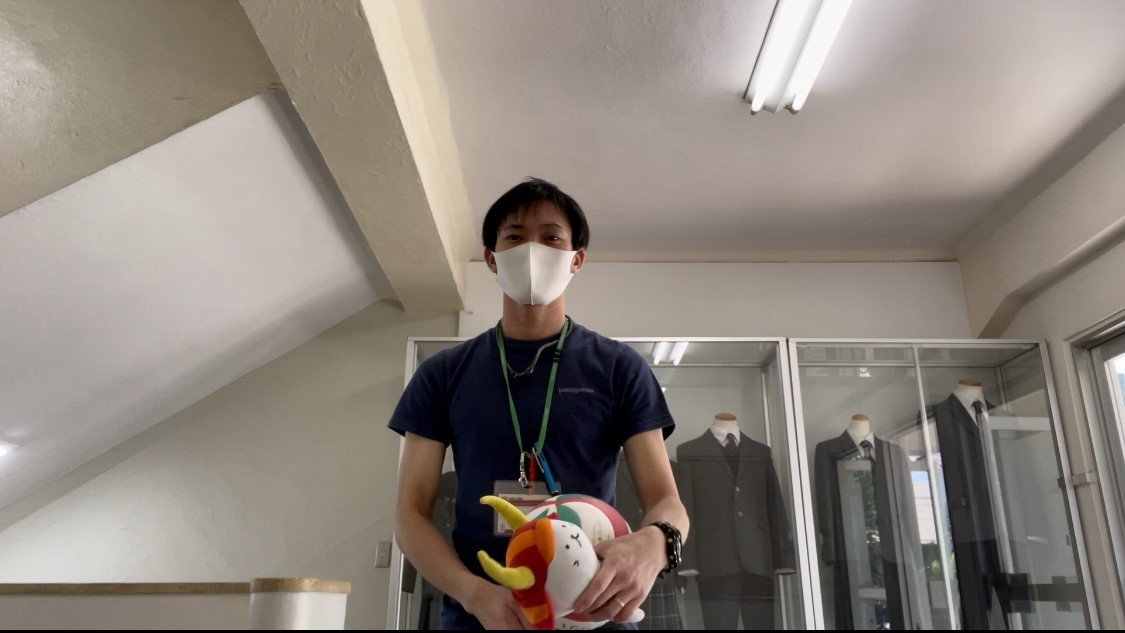
吃音症には言いやすい名前と言いにくい名前があるため、ハルキさんは本番前に何度も練習。吃音症が現れるたび、子どもたちに申し訳なくなり、体育館の裏でひとり涙を流した日もあった。
「放課後、暗い体育館にマイクを設置し、毎日毎日ひとりで練習しました。それでも吃音症は治りませんでした」
すっかり自信を喪失したハルキさんは、学校長に「僕なんかでいいのですか?」と相談。すると、返ってきたのは「全然問題ないよ。クヨクヨするなんてあなたらしくないじゃないか!」という励ましの言葉だった。
その言葉に背中を押され、担任として「この子たちの名前を呼ぶのは人生で最後になるかもしれないから、吃音なんて気にしないで心をこめて呼んであげよう」と思えるようになったという。
「他にも、困難を感じる場面はありました。でも、そのたび、決して逃げず、立ち向かっていったんです。当然、成功も失敗もありましたが、少しずつ自信をつけていけました」
そうしたハルキさんの努力は世間からも注目され、その生き方が新聞で取り上げられたり、講演を依頼されたりするようになった。
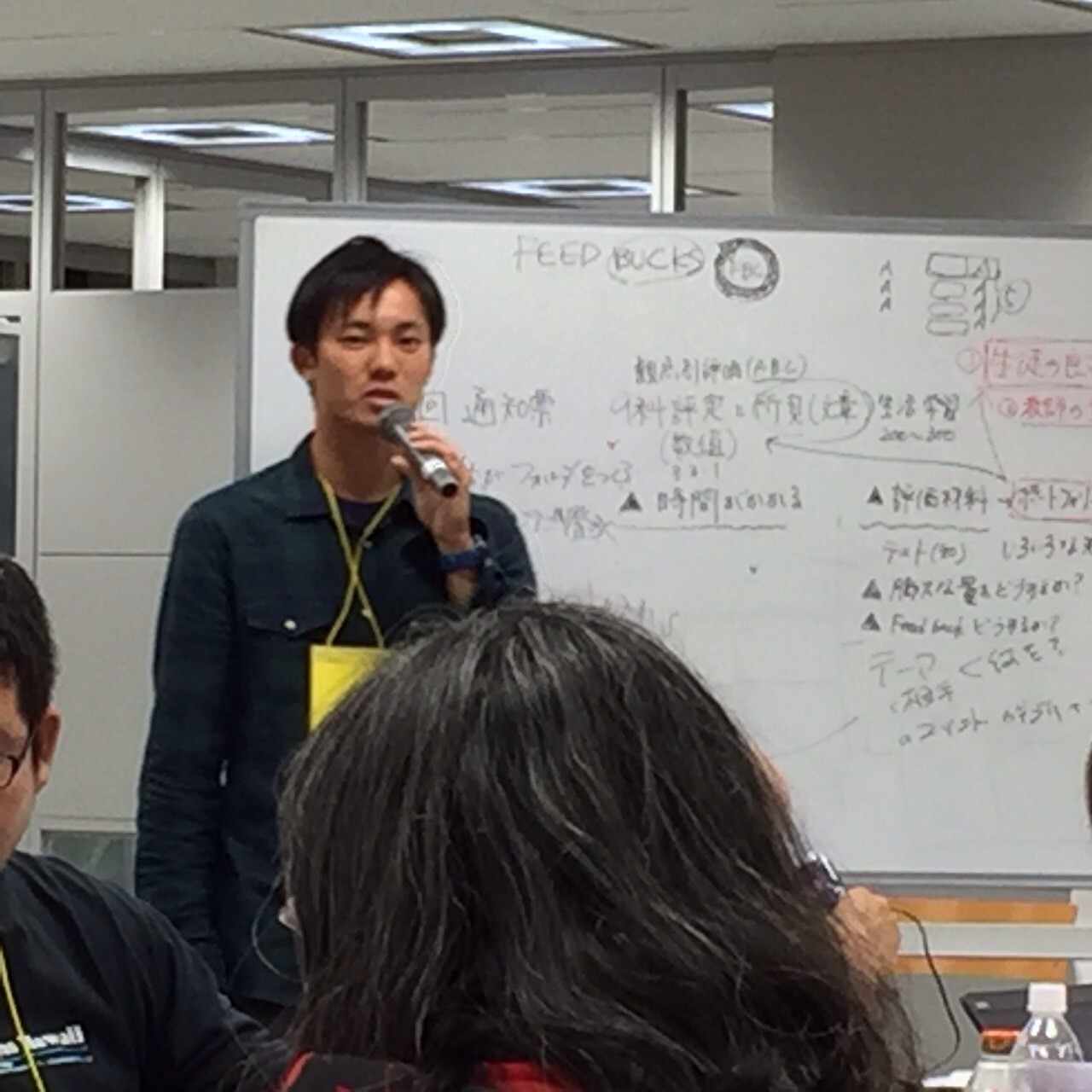
「吃音症を抱える児童やその保護者から個別に相談を受けるようにもなりました。吃音があったからこそ得た、学びや出会いに感謝しています」
吃音症が「眼鏡」のような自然なものになってほしい
吃音症と付き合う上で、ハルキさんには意識していることがある。例えば、新しい職場になった時には最初の挨拶で症状を打ち明ける。全校児童には着任式の時に、保護者には学級通信などで伝えているそう。
「勇気のある行動と言われますが、個人的には自分を守るためであるので、あまりプレッシャーになりません。日常生活でも、吃音症であることを初めに伝えています。すると、互いに理解がある状況になるので、心が軽い。吃音症をもっと知ってもらうためにも、他人に伝えることは大切なことだと思っています」
現在、ハルキさんには大きな夢がある。それは、「吃音症は障害」という意識をなくすことだ。

「かつて、視力がよくない人は障害者と見られていたこともあるという話を聞きました。でも、今は眼鏡によって視力がカバーできますし、眼鏡はファッションアイテムのひとつとして活躍し、ビジネスも生まれている。現代の私たちは、眼鏡をしている人に対して何も気にせず接している。これは、まさしく障害が消えた瞬間です」
だから、吃音症も眼鏡のように特別視されないようになってほしい。そして、吃音症のアナウンサーやYouTuberも、ごく普通に活躍できる社会にしていきたい――。そう願うハルキさんは自身が苦手なものを挙げ、吃音症への理解を呼びかける。
「僕は電話がとても苦手です。上手く話すことができず、相手から怒られて切られたことがあります。吃音症は知らなくて当然なのですが、もし当事者と接したら、『この人は吃音で悩みがあるのかも』と、少しでも思ってくれたら嬉しいです」



