2020年4月、新型コロナウイルス感染拡大のために日常生活は一変。人に会いたくても会えない状況下で閉塞感は強まり、人々の心にもさまざまな影響を及ぼしました。
そんな非日常だからこそ「“日常の言葉”を読みたい」と思ったのが、文化施設職員の佐藤友理さんと鮮魚店勤務の中田幸乃さん。自分たちに加えて、日本と台湾に暮らす8人から日常について綴ってもらった原稿を集め、『まどをあける』というエッセイ集を作りました。

筆者の住む場所は、山梨県の八ヶ岳、徳島県の祖谷、東京都、宮城県などの日本各地と台湾。内容もさまざまで、二十日大根の種が芽吹く日々で感じたこと、実家で家族と共に過ごす心情、誰かと会って話す日常への思いなど。筆者それぞれの「日常」が、優しい視線で綴られています。
この創刊号はフリーペーパーとして全国39の書店に設置され、好評のうちに配布終了。そして約9か月後の2021年3月には、有料版の第2号を発行しました。今回は創刊号発行まで道のりと、2号制作にまつわる話を、オンラインで取材しました。
落ち着いて出てくる言葉が読みたかった
愛らしい鳥のイラストと、柔らかな色合いの表紙が印象的。ページを開くと、はじめに「遠くで暮らす誰かの、目の前の景色を想像する」というテーマが飛び込んできます。
“試案しながら書こうとしたときにだけ出てくる言葉、
そこに宿る何かに触れたくて、
遠くで暮らす人たちに短いエッセイを書いてもらいました”
(『まどをあける』創刊号1ページ目より)

「Webマガジンやデジタルはスピードが速く、多くの人たちに一気に読んでもらえる利点がありますが、今回はそこじゃない。素早いスピードで書き上げられるものでなはく、まるで1本のエッセイを書くために生まれるような、落ち着いて出てくる言葉が読みたかったんです」

2020年4月、宮城県名取市に住む佐藤さんは在宅勤務となり、家で過ごす時間が増えました。テレビやインターネットで流れる情報を前に、ふと疑問を抱きました。
「この閉塞感に満ちた状況で、本当はみんな何を考えているんだろう?と。あの頃、自分の目の前しか見えていない感じがあったんです」
また、当時愛媛県に住んでいた中田さんは、メディアの影響を受けた父親の発言と衝突し「まるで何を言っても批判されるような不安」を抱いていました。家族以外の誰かの言葉、それも文章を書く時のような言葉を聞きたくなったと言います。

2人はかつて、香川県の別々の書店で働いていたことがあり、書店仲間として知り合った仲でした。
電話で不安や思いを語り合う中、「本を作ろう」と提案したのは佐藤さん。「私たちが読みたい言葉を読みたかったんです。それは手紙のようでもあり、その人の本心がにじむような文章。書いたら消して直して読み直してと、冷静になれる過程を踏まえて生まれた文章」と佐藤さんは言います。
閉塞感の中で生まれた“強い言葉”ばかりに流されたくない。電話やSNSとは違う、その人が描いた文章を読みたい。佐藤さんと中田さんは「立ち止まって書かれた言葉を書いてくれそうな人」たちを探し始めました。2人には、書店をやっていたから出会えた人たちが全国にいました。
「この人は今どうしてるかなぁ、会いたいなぁ、と思う人に声をかけました。遠くにいる気の置けない人たちは、今、何を考えているんだろう。遠くにいる人の日常を感じたかったんです」
そして2020年4月下旬に企画をまとめ、5月に依頼を出しました。2週間の執筆期間を経て、6月には印刷物として完成しました。
『これだよー!こういうのが読みたかった!』
依頼したその日に、早速、山梨県の八ヶ岳山麓の町に住む石垣純子さんの原稿が届きました。石垣さんは「私の原稿がエンジンになって、他の人たちへの依頼になれば」という思いを込めていたと言います。

“山笑い、鳥はさえずる”というタイトルを持つエッセイの始まりは「こんにちは。お元気ですか」。まるで手紙のように綴られた、八ヶ岳山麓の情景や日常が浮かぶような文章。日々の移ろいを感じるなか、「生」を確かめる喜びが綴られていました。
「石垣さんの書く文章は、風が吹くような感じだったんです。読んだ瞬間『これだよー!こういうのが読みたかった!』って叫びました」
佐藤さんも中田さんも喜びます。そして、石垣さんの原稿のおかげで「自分たちは、身の回りの自然を考えられる状況ではなかったんだ」と再確認。自分たちが作ったコンセプト「遠くで暮らす誰かの、目の前の景色を想像する」も、改めて腑に落ちました。

エッセイにイラストを添えたのが、香川県高松市に住む上野さん。中田さんが香川に住んでいたときに知り合った、イラストレーターです。上野さんは畑作業で苗物の水やりをしたり絵を描く生活リズムの中で、原稿を読み、執筆者の生活を想像して、日常にあるいいものをテーマに絵に起こしました。「出かけている気分になり、広がる感覚」で描かれた挿絵は、執筆者にも好評でした。
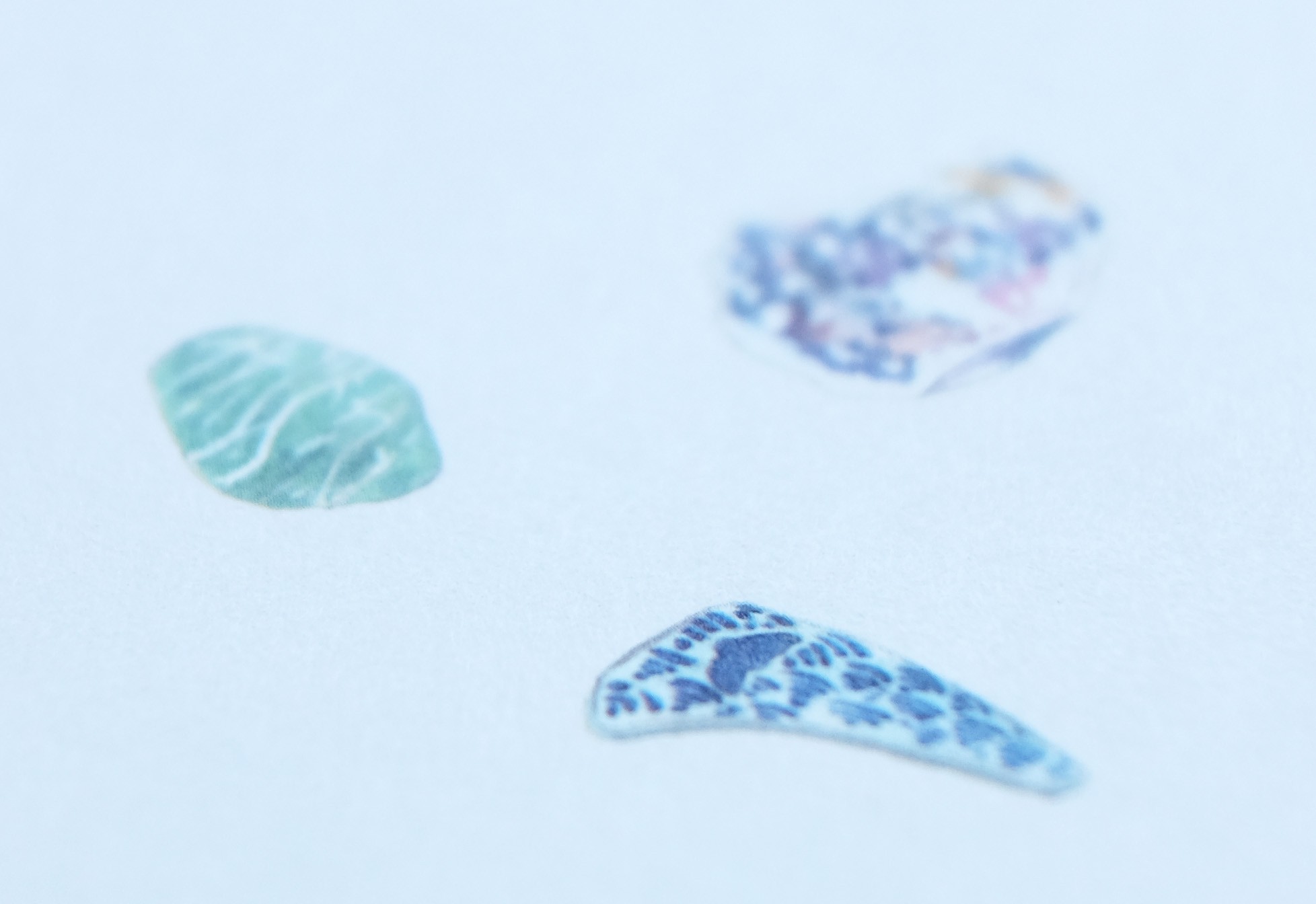
本を通じての再開と出会い
創刊号が完成し、全国の縁ある書店に配布された『まどをあける』。人と会いにくい状況が続く中、佐藤さんと中田さんは多くの人たちからメールやSNSで感想を受け取りました。
「この時初めて、実感ある言葉としての“会話”ができ、手ごたえを感じました。またTwitterに、知らない誰かの言葉と『まどをあける』の表紙を撮った写真が載っていて。本の感想をもらえるのが、こんなに嬉しいものなんだと気づきました」
そして自分たちと同じように、何気ない日常の言葉を読みたかった人もいたのだと気づきました。本を通じての再会と出会いが、そこにはありました。
言葉は人を救う
2020年末、3人は2号の制作に取り掛かりました。本屋の店主、バーのマスター、ラジオパーソナリティ、アルバイト……まだ行ったことのない店の人、感想をくれた人、久々に連絡をくれた人たちが執筆します。コンセプトも創刊号と変わらず「遠くで暮らす誰かの、目の前の景色を想像する」。

しかし2号の制作は大変で、「グラデーションのある戸惑いに包まれた中での制作」だったと振り返ります。
「創刊号の時は書くことが見つかりやすかった。日本全国に共通した切迫感があったからだと思います。でも2021年は悩みました。“日常”に、地域差が出てしまっている。『書くことで誰かを傷つけるんじゃないだろうか』って」
テレビのニュースでは、都市部の新型コロナウイルス感染者の膨大な数が報じられていました。遠くの人たちへの思いやりと、生みの苦しみが混在。どうすれば誰も傷つけないだろうと戸惑う中でも、「自分たちが読みたい言葉を読みたい」と、言葉の力を信じた3人。創刊号と同じく“立ち止まって書かれた”言葉が綴られた2号は、2021年3月に無事に発行されました。
今も、何気ない日常の言葉を読みたい人もいるはずだ。本を通じての再会と出会いを信じて、再び3人の『まどをあける』時がやってきました。
「言葉は人を救うんです」佐藤さんは力強く語りました。


